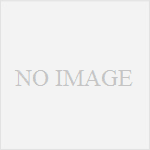宅建士試験で出題されそうな税その他の重要数字のみをまとめています。
教材購入者専用ページ内にあります【数字問題】の一部分だけを掲載しています。
また、復習まとめ集には全て掲載しておりますので、教材購入者の方は、復習まとめ集を完璧にしてください。
印紙税
| 数字の暗記編 |
|
平成26年4月1日以降に作成した受取書については、記載金額が5万円未満のものについて非課税となります。平成26年3月31日以前に作成した受取書については、記載金額が3万円未満のものについて、非課税となります。
|
| 数字の確認編 |
|
平成26年4月1日以降に作成した受取書については、記載金額が( )万円未満のものについて非課税となります。平成26年3月31日以前に作成した受取書については、記載金額が( )万円未満のものについて、非課税となります。
|
固定資産税
| 数字の暗記編 |
- 質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者が、固定資産税の納税義務者となります。
- 1月1日時点での固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)が、課税標準となります。
- 毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿や家屋価格等縦覧帳簿を、固定資産税の納税者の縦覧に供しなければなりません。
- 標準税率は、1.4%となります。
- 納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければなりません。
- 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めます。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができます。
- 土地の場合、課税標準が30万円未満のときには、原則、固定資産税が課されません。
- 家屋の場合、課税標準が20万円未満のときには、原則、固定資産税が課されません。
- 償却資産の場合、課税標準が150万円未満のときには、原則、固定資産税が課されません。
- 住宅用地の200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、住宅用地の価格の6分の1が、課税標準となります。
- 住宅用地の200平方メートル超の部分については、住宅用地の価格の3分の1が、課税標準となります。
- 下記の全ての要件に該当する新築住宅が、3階建て以上の中高層耐火建築物については、5年間又それ以外の住宅については、3年間にわたって、床面積の120平方メートルまでの住宅部分について、固定資産税額の2分の1が減額されることになります。
(1)床面積の2分の1以上が、居住の用に供されていること。なお、この要件は、併用住宅(店舗兼住宅等)の場合です。
(2)居住の用に供する部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下(戸建て以外の賃貸住宅の場合には、40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。
|
| 数字の確認編 |
- 質権又は( )年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者が、固定資産税の納税義務者となります。
- ( )時点での固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)が、課税標準となります。
- 毎年( )から、( )又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿や家屋価格等縦覧帳簿を、固定資産税の納税者の縦覧に供しなければなりません。
- 標準税率は、( )%となります。
- 納税通知書は、遅くとも、納期限前( )日までに納税者に交付しなければなりません。
- 固定資産税の納期は、( )月、( )月、( )月及び( )月中において、当該市町村の条例で定めます。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができます。
- 土地の場合、課税標準が( )万円未満のときには、原則、固定資産税が課されません。
- 家屋の場合、課税標準が( )万円未満のときには、原則、固定資産税が課されません。
- 償却資産の場合、課税標準が( )万円未満のときには、原則、固定資産税が課されません。
- 住宅用地の( )平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、住宅用地の価格の( )が、課税標準となります。
- 住宅用地の( )平方メートル超の部分については、住宅用地の価格の( )が、課税標準となります。
- 下記の全ての要件に該当する新築住宅が、( )階建て以上の中高層耐火建築物については、( )年間又それ以外の住宅については、( )年間にわたって、床面積の( )平方メートルまでの住宅部分について、固定資産税額の( )が減額されることになります。
(1)床面積の( )以上が、居住の用に供されていること。なお、この要件は、併用住宅(店舗兼住宅等)の場合です。
(2)居住の用に供する部分の床面積が、( )平方メートル以上( )平方メートル以下(戸建て以外の賃貸住宅の場合には、( )平方メートル以上( )平方メートル以下)であること。
|
この続きは、教材購入者専用ページにてご確認ください。

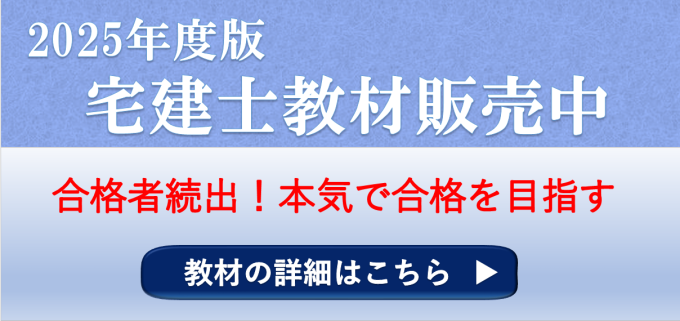
-680x156.png)
-680x155.png)
-680x151.png)