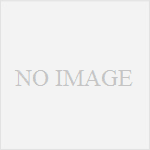平成27年度宅建士試験に対応するために、宅建合格広場のテキスト、問題集、重要論点について、法改正に伴う変更を行なっています。
宅建士試験では、法改正部分が出題される可能性もあるので、試験当日までに法改正部分を把握して下さい。法改正部分が宅建士試験で出題された場合、多くの受験生が正解することができるので、皆さんも、必ず、正解できるように準備していきましょう。
このページでは、平成27年度法改正に伴う変更部分について記載していきます。宅建士試験合格のために、ご活用下さい。
消費税免税事業者の報酬の改正
消費税免税事業者の報酬 改正前
宅建業者の報酬を計算する際、宅建業者が、消費税免税事業者の場合、4%の上乗せがなされていました。
消費税免税事業者の報酬 改正後
4%の上乗せ部分が、改正により3.2%となりました。
消費税免税事業者の報酬 改正後の問題
下記の問題は、正しいですか?それとも誤っていますか?
宅建業者A社(消費税免税事業者)は貸主Bから宅地の貸借の媒介の依頼を受け、宅建業者C社(消費税免税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約(1カ月分の借賃は10万円)を成立させた。A社及びC社が受領することができる報酬の限度額は、A社とC社あわせて10万3,200円となる。
消費税免税事業者の報酬 改正後の問題の解説
A社とC社あわせて、借賃の1カ月分を限度として報酬を受け取ることができます。
なお、A社とC社は、消費税免税事業者なので、3.2%(=この部分が改正部分です。)を上乗せします。よって、10万円×1.032(=この部分が改正部分です。)=103,200円となります。
よって、本問は、正しいです。
不動産取得税の改正
課税標準の特例 改正前
宅地評価土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成18年1月1日から平成27年3月31日までの間に行なわれた場合に限り、当該土地の価格の2分の1となります。
課税標準の特例 改正後
「上記の平成27年3月31日」の箇所が、法改正により、平成30年3月31日になります。
つまり、3年間延長されます。
標準税率 改正前
平成18年1月1日から平成27年3月31日までに取得した土地と住宅用家屋についての不動産取得税の税率は、3%となります。
標準税率 改正後
「上記の平成27年3月31日」の箇所が、法改正により、平成30年3月31日になります。つまり、3年間延長されます。
住宅の特例 改正前
下記の要件に該当する中古住宅を取得した場合、当該住宅の価格から、当該住宅の新築年月日に応じて、一定の控除額(最高額1,200万円)が控除されます。
- 当該住宅を取得した者が、個人であること。
- 個人が、当該住宅を自己の居住用に供する目的で取得すること。
- 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
- 「築20年(耐火建築物については25年)以内であること」、「昭和57年1月1日以降に建築されたこと」、「新耐震基準に適合していること新耐震基準に適合していることを証明したこと」のいずれかに該当すること。
住宅の特例 改正後
【改正前】上記4の「築20年(耐火建築物については25年)以内であること」が削除されました。
つまり、改正後は、「昭和57年1月1日以降に建築されたこと」、「新耐震基準に適合していること新耐震基準に適合していることを証明したこと」のいずれかに該当することが、特例の適用要件となります。
贈与税の改正
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税 改正前
親から住宅取得等資金の贈与を受けた子供(贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上である子供に限ります)が、一定の要件を満たせば、親の年齢に関係なく、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
この特例は、平成15年1月1日から平成26年12月31日までに贈与受けた場合に適用されていました。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税 改正後
「上記の平成26年12月31日」の箇所が、法改正により、平成31年6月30日になります。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 改正前
直系尊属(父、母、祖父母など。年齢は何歳でもよいです)から住宅取得等資金の贈与を受けた贈与者の20歳以上である直系卑属(子供・孫など)は、一定の要件を満たせば、平成26年中の贈与については、暦年課税の基礎控除である110万円の他に、相続時精算課税の特別控除である2,500万円の他に、500万円(質の高い住宅家屋については、1,000万円)が非課税となります。
なお、この規定は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までに贈与受けた場合に適用されていました。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 改正後
直系尊属(父、母、祖父母など。年齢は何歳でもよいです)から住宅取得等資金の贈与を受けた贈与者の20歳以上である直系卑属(子供・孫など)は、一定の要件を満たせば、平成27年中の贈与については、暦年課税の基礎控除である110万円の他に、相続時精算課税の特別控除である2,500万円の他に、1,000万円(質の高い住宅家屋については、1,500万円)が非課税となることになります。
なお、この規定は、平成24年1月1日から平成31年6月30日までに贈与受けた場合に適用されることになります。
宅建業法の改正
平成27年4月1日から宅建業法の一部を改正する法律が施行されます。下記から、宅建試験上、改正に伴う重要部分について記載していきます。
- 宅地建物取引主任者が宅地建物取引士に変更され、宅地建物取引主任者証が宅地建物取引士証に変更され、宅地建物取引主任者資格試験が宅地建物取引士資格試験に変更されました。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許の欠格要件及び登録の欠格要件に該当することになりました。また、暴力団員等がその事業活動を支配する者についても、免許の欠格要件に該当することになりました。
- 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。」という規定が設けられました。
- 「宅地建物取引士は、取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」という規定が設けられました。
- 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければなりません。
- 重要事項の説明時には、取引関係者からの請求がなくても、取引士証を提示しなければなりません。また、重要事項の説明時以外のときにおいても、取引関係者から請求があれば、取引士証を提示しなければなりません。なお、「取引士証の提示の際、住所欄にシールを貼ったうえで提示してもよい。」ことになりました。
容積率の改正
容積率の計算 改正後
エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積を容積率の算定における延べ面積に算入しないことになりました。
※上記の規定は、エスカレーターや小荷物専用昇降機については、適用対象外です。

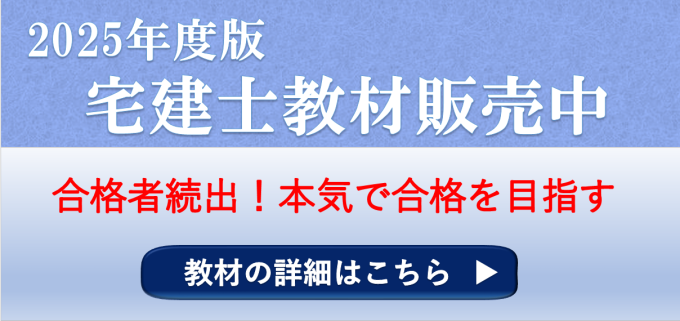
-680x125.png)
-680x125.png)
-680x151.png)