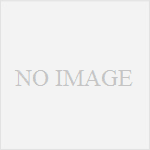2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問5の問題(代理)と解答・解説です。
問5:問題(代理)
AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。
- AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
- BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
- AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
- BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
問5:解答・解説(代理)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、無権代理行為となります。つまり、原則として、A・C間の法律行為の効果は、本人Bに帰属しません。(追認などがあれば、別ですが・・・)
↓
代理権の濫用の流れは、
相手方を保護する観点から、代理権が濫用された場合においても、代理行為は、原則として、有効となります。
↓
しかし、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであった場合には、相手方を保護する必要はありませんので、無権代理行為となります。 - 誤り
本肢は、「BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し」となっていますので、「代理権授与の表示による表見代理」の話となります。
↓
さらに、「Aが代理権の範囲内の行為をした」となっていますので、「代理権の範囲内」の話となります。
↓
相手方Cが善意無過失であれば、「代理権授与の表示による表見代理」が成立しますが、
本肢は、「相手方Cが悪意」となっていますので、「代理権授与の表示による表見代理」が成立しません。
つまり、本人Bは、相手方Cに対して責任を負いません。(追認などがあれば、別ですが・・・) - 正しい
本肢は、「詐称して」となっていますが、これは、本人Bに落ち度(帰責性)はありません。つまり、表見代理の話は出てきません。(弁済の話は別の話です)
↓
表見代理の話が出てきませんので、原則どおりの無権代理行為となります。つまり、原則として、法律行為の効果は、本人Bに帰属しません。(追認などがあれば、別ですが・・・) - 誤り
本肢は、「BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った」となっていますので、「代理権消滅後の表見代理」の話となります。
↓
さらに、「Aが行った代理権の範囲内の行為」となっていますので、「代理権の範囲内」の話となります。
↓
相手方Cが善意無過失であれば、「代理権消滅後の表見代理」が成立しますが、
本肢は、「相手方Cが有過失」となっていますので、「代理権消滅後の表見代理」が成立しません。
つまり、本人Bは、相手方Cに対して責任を負いません。(追認などがあれば、別ですが・・・)
解答:3
|
フルセット教材詳細・お申込み |
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております
|

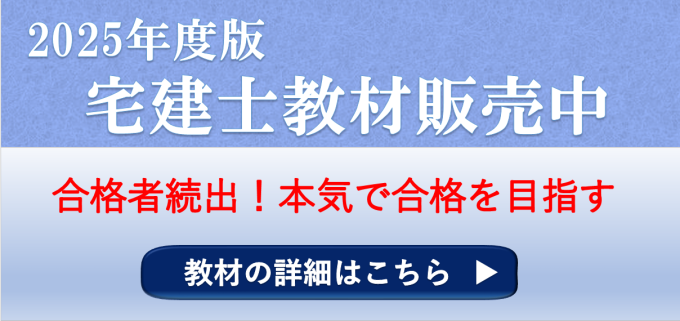
-680x125.png)
-680x125.png)
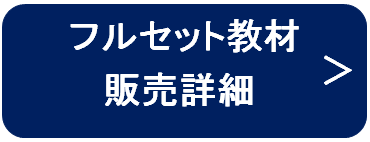
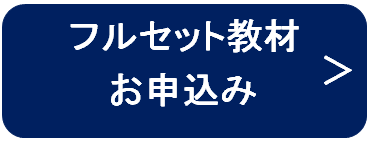
-680x151.png)