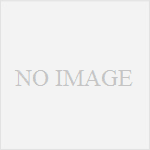制限行為能力者の種類
制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に分類されます。
単独で有効に契約などの法律行為をなし得る能力のことを行為能力といいます。
成年被後見人
1.成年被後見人とは
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者のことをいいます。
|
【補足】
- 家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等の請求により後見開始の審判をすることができます。
- 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、成年後見人が付されます。
- 後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護していくための手続のことです。
- 後見開始の審判の取消しが行われた場合、成年被後見人に該当しなくなります。
|
2.成年被後見人が行う行為
【原 則】
成年被後見人が単独で行った法律行為及び法定代理人の同意を得て行った法律行為は、取り消すことができます。
|
【補足】
- 法定代理人とは、成年後見人のことです。
- 法人であっても法定代理人になることができます。
- 成年後見人の同意を得て行った法律行為であっても、取り消すことができます。なぜなら、同意を与えたとしても、成年被後見人自身が、単独でその同意に従った適切な行為ができない可能性が高いためです。
- 成年後見人は、複数の者を選任することもできます。
- 成年後見人には、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)があり、この義務を怠ると損害賠償責任を負うことになります。
|
【例 外】
成年被後見人が単独で行った日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません。
3.法定代理人の権利
成年後見人には、取消権、代理権、追認権があります。
|
【補足】
-
成年後見人には、同意権がありません。なぜなら、同意を与えたとしても、成年被後見人自身が、単独でその同意に従った適切な行為ができない可能性が高いためです。
-
成年被後見人が居住している建物、その敷地について、成年後見人が、成年被後見人に代わって、売却や賃貸や賃貸借の解除や抵当権の設定等をする場合、家庭裁判所の許可が必要となります。
- 後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。しかし、後見監督人がいる場合には、その必要がありません。
|
この続きは、
教材購入者専用ページ内にあるテキストをご利用ください。
|
販売教材の詳細はこちら
|
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております
|

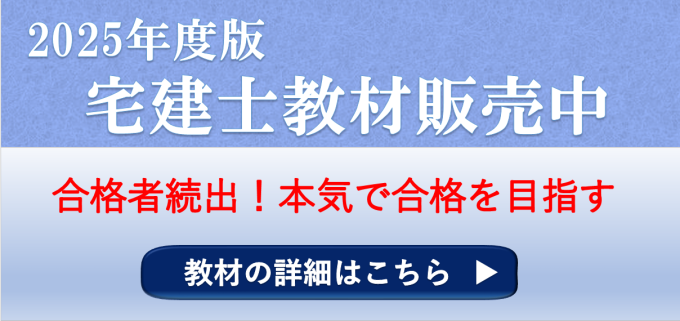
-680x125.png)
-680x125.png)
.png)
.png)
-680x151.png)