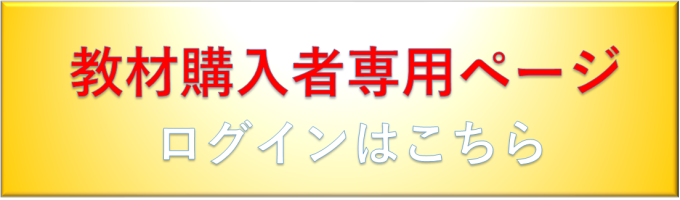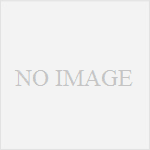毎年、法改正部分が宅建士試験で出題されております。2026年度(令和8年度)の宅建士試験を受験される方は、必ず、確認しておきましょう。
宅建士合格広場から販売している教材に関しては、法改正に伴う変更を行なっていますので、是非ご利用ください。
※このページは、改正論点の一部のみを掲載しております。この他にも改正されておりますので、教材購入者の方は、専用ページ内&販売教材でご確認し、ポイントを押さえてください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)
目次一覧
宅地建物取引業法
宅建業免許等
【改正前】
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができません。
【改正後】
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができません。
※「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。具体例として、上記のものを記載しましたが、宅建業法以外も同じです。
権利関係
不動産登記法
【新設】
- 相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、特定の者が所有権登記名義人として記録されている不動産(そのような不動産がない場合には、その旨。)を一覧的にリスト化し、証明する制度(所有不動産記録証明制度)が新設されました。
所有不動産記録証明書は、下記の者が、法務局の登記官に手数料を納付することにより発行することができます。
1)本人(個人・法人)
自らが所有権登記名義人として記録されている不動産について請求できます。
2)相続人その他の一般承継人
被相続人その他の被承継人に係る不動産について請求できます。 - 登記官は、他の公的機関(住基ネットなど)から取得した所有権の名義人の死亡情報を、職権で、登記簿に符号で表示することができます。
- 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。
※スマート変更登記の手続をしておけば、住所等の変更があるたびに登記申請をしなくても、登記官の職権で住所等の変更登記がされます。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
集会の決議
【改正前】
建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は全区分所有者の多数決によります。
【改正後】
建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は集会出席者の多数決によります。また、裁判所が認定した所在等不明区分所有者(必要な調査を尽くしても氏名や所在が不明な者)は決議の母数から除外されます。
例:全区分所有者の多数決による普通決議(過半数)の場合
| 出席 |
Aさん(賛成)
|
Bさん(賛成)
|
Cさん(反対)
|
| 欠席 |
Dさん(無関心)
|
Eさん(所在不明)
|
改正により賛成2/3(集会出席者)で否決されます。改正前は、2/5(全区分所有者)でした。
共用部分の変更の決議
【改正前】
共用部分の形状や効用を変える行為については、著しい変更の場合(重大な変更)には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上(区分所有者の定数のみ規約で過半数まで引下げが可能)の多数による集会の決議で決します。
【改正後】
共用部分の形状や効用を変える行為については、著しい変更の場合(重大な変更)には、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上(規約で過半数まで引下げが可能)の多数による集会の決議で決します。なお、「共用部分の設置・保存に瑕疵があることによって他人の権利・利益が侵害され又は侵害されるおそれがある場合において、その瑕疵の除去に必要な共用部分の変更」や「バリアフリー化のために必要な共用部分の変更」は、各3分の2以上の賛成で足ります。
管理不全の専有部分・共用部分の管理制度
【新設】
区分所有者が専有部分・共用部分を管理せず、放置していることで他人の権利が侵害されるおそれがある場合には、利害関係人が裁判所に申し立てることで、管理人を選任することができます。
決議の多数決要件のまとめ
| 決議事項 | 決議の多数決 |
| 共用部分の変更 | 出席区分所有者及びその議決権の4分の3(規約で過半数まで引下げ可) 一定の事由がある場合は、3分の2 |
| 共用部分の変更に伴う専有部分の使用等 | 規約の定めがあることを前提に、出席区分所有者及びその議決権の4分の3(規約で過半数まで引下げ可) 一定の事由がある場合は、3分の2 |
| 共用部分の復旧 | 出席区分所有者及びその議決権の3分の2 |
| 建替え、建物更新(一棟リノベーション)、取壊し | 区分所有者及び議決権の5分の4 一定の事由がある場合は、4分の3 |
| 共用部分の管理等 | 出席区分所有者及びその議決権の過半数(規約で別段の定め可) |
| 共用部分の管理に伴う専有部分の使用等 | 規約の定めがあることを前提に、出席区分所有者及びその議決権の過半数(規約で別段の定め可) |
| 区分所有法は、上記以外にも改正論点がたくさんあります。教材購入者の方は、専用ページ内や復習まとめ集等でご確認ください。 |
相続/公正証書遺言
【改正前】
公正証書遺言は、公証役場に出頭して嘱託を行い、書面で作成・保存をしなければなりません。
【改正後】
公正証書遺言は、インターネットを利用して、電子署名を付して嘱託を行うことが可能であり、原則、電子データで作成・保存をしなければなりません。
税その他
住宅金融支援機構法
【新設】
住宅金融支援機構の業務の融資に下記が追加されました。
- マンションの更新、又はマンションの更新がされた後のマンションで、当該マンションの更新がされた後に人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該マンションの更新又はマンションの更新がされた後のマンションの購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付け
- 要除却等認定マンションの除却等に必要な資金の貸付け
上記の内容以外に民法なども改正されておりますので、教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等でご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)
改正論点は、古い教材では抜け落ちている部分が沢山あります。
過去問を解いていても、この改正論点を抑えることはできません。
改正論点の対策が合否を分けることがありますので、最新の改正を押さえてください。
試験後に後悔しないために、今お持ちの教材を見直してみましょう。
当教材は、古い教材では拾えない改正論点も、しっかりカバー!!
今の教材に不安がある方は、ぜひ一度ご確認ください。
|
販売教材の詳細はこちら |
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |

-e1760533051531.png)
-680x156.png)
-680x155.png)
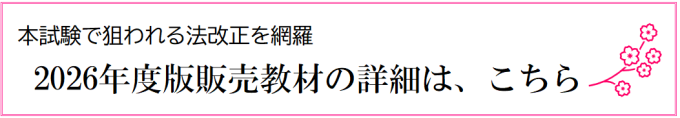





.png)
.png)