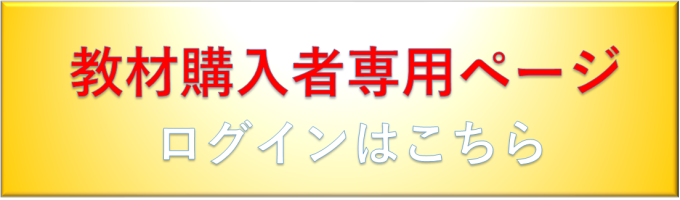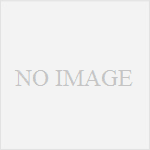このページは、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にあるポイント解説ページの一部を掲載しています。
今回は、民法の意思表示の受領能力を解説します。
意思表示の受領能力
|
【民法98条の2:意思表示の受領能力】 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。 1.相手方の法定代理人 |
では、具体的に見ていきます。
上記の規定は、
未成年者、成年被後見人、意思無能力者が、意思表示を行った場合の規定ではなく、
相手方が、未成年者・成年被後見人・意思無能力者に対し、意思表示を行った場合の規定と考えてください。
↓
未成年者、成年被後見人、意思無能力者には、受領能力、つまり、意思表示の内容を理解する能力がありません。
なお、被保佐人・被補助人には、受領能力があると考えられています。
↓
「相手方→未成年者・成年被後見人・意思無能力者」に意思表示を行った場合、
意思表示の内容を理解する能力がありませんので、
「意思表示を行いましたよ!」と未成年者・成年被後見人・意思無能力者に対抗(主張)することができません。
※なお、未成年者・成年被後見人等側から、「意思表示を受けましたよ!」と、主張することができます。(本人側から言うのですから、問題は発生しない!)
ただし、
その法定代理人(親等・成年後見人)等がその意思表示を知ったのなら、意思表示の効力を主張することができます。
次は、簡単に、解説します。
未成年者Aは、B所有の甲不動産を買いたいな!と思っていました。
↓
Bは、Aの親から甲不動産の買受けの申込みを受けました。
↓
Bは、「売却しますよ!」という意思表示を、本人であるAに対して行いました。
↓
この場合、契約の成立を主張することができません。
↓
どのようにすれば、契約の成立を主張することができるのか?についてですが、
Bは、Aの法定代理人(親等)に対して、「売却しますよ!」という意思表示を行う必要があります。
問題にチャレンジ
AのBに対する契約の解除の意思表示に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ、Bがその通知書を受け取り、Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合、Aは、その意思表示をもってBに対抗することができる。
↓
↓
↓
↓
解答:正しい
Bは未成年者で受領能力がありませんので、表意者(A)は意思表示の到達を主張することができません。
しかし、本問では、
「Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った」と記載されていますので、
Aは、意思表示の到達を主張することができます。
問題にチャレンジ
次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
↓
↓
↓
↓
解答:誤り
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができません。
本問は、「または制限行為能力者」となっており、被保佐人や被補助人を含んでいますので、誤りです。
≫≫≫民法解説目次ページに戻る
|
販売教材の詳細はこちら |
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |

-e1760533051531.png)
-680x156.png)
-680x155.png)
.png)
.png)