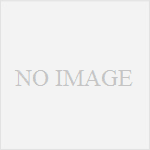時効
時効には、取得時効と消滅時効があります。
|
【補足】
- 取得時効とは、時効によって権利を取得できる制度です。所有権・用益物権(=地上権、地役権等)・不動産賃借権等が取得時効できます。
- 消滅時効とは、時効によって権利が消滅する制度です。
|
取得時効の成立要件
所有権と所有権以外の取得時効が成立するための要件について見ていきます。
所有権の取得時効が成立するための要件
- 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意無過失以外であるときは、その所有権を取得する。
- 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意無過失であるときは、その所有権を取得する。
|
【補足】
1.所有の意思をもって占有について
2.平穏に、かつ、公然と占有について
- 「平穏に占有」とは、強迫等による占有ではないということです。
- 「公然と占有」とは、隠匿による占有ではないということです。
3.善意無過失について
- 善意無過失とは、自分に所有権があると過失なく信じることです。
- 占有開始時に善意無過失であるときは、その後、自分に所有権がないと知った場合においても、その人は、善意無過失ということになります。
|
占有の承継があった場合
|
【例題1】
Aが所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然とC所有の建物を占有していた。その後、Aは、取得時効が成立するまでの間に、その建物の占有者がBに移った場合、Bは、何年で取得時効が完成するのか。(=なお、この例題の大前提は、実際には、その建物の所有者は、CではなくDと考えます)
【解答・手順】
- Bは、1人での占有で取得時効を成立させていくのか、Aの占有期間も合わせて取得時効を成立させていくのかは自由に選択できます。
- Aの占有期間も合わせて取得時効を成立させていく場合には、Aの事情(悪意・善意・過失の有無)もBに引き継がれることになります。例えば、Aが占有開始時に善意無過失であるときは、Bが占有開始時に善意無過失でなくても、Aの善意無過失がBに引き継がれて10年の占有で取得時効が成立します。
【例題2】
占有開始時に善意無過失のAが所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と5年間、C所有の建物を占有していた、その後、AからBにその建物の占有が移った場合、占有開始時に悪意(=自分に所有権がないと知っていた)のBは、何年で取得時効が完成していくのか。
【解答・手順】
- Bは、1人での占有で取得時効を成立させていく場合、占有開始時に悪意なので20年の占有が必要となります。
しかし、Aの占有期間も合わせて取得時効を成立させていく場合、Aの善意無過失もBに引き継がれるので10年の占有で取得時効が成立します。
- したがって、Bは、その建物を5年間占有すると、Aの占有期間と合わせて10年となり取得時効が成立します。なお、この場合においても、Bは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有する必要があります。
【例題3】
占有開始時に悪意のAが所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と5年間、C所有の建物を占有していた。その後、AからBにその建物の占有が移った場合、占有開始時に善意無過失のBは、何年で取得時効が完成していくのか。
【解答・手順】
- Bは、1人での占有で取得時効を成立させていく場合、占有開始時に善意無過失なので10年の占有が必要となります。しかし、Aの占有期間も合わせて取得時効を成立させていく場合、Aの悪意もBに引き継がれるので20年の占有で取得時効が成立します。
- したがって、Bは、その建物を15年間占有すると、Aの占有期間と合わせて20年となり取得時効が成立します。なお、この場合においても、Bは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有する必要があります。
|
この続きは、
教材購入者専用ページ内にあるテキストをご利用ください。
|
販売教材の詳細はこちら
|
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております
|

-680x177.png)
.png)
.png)