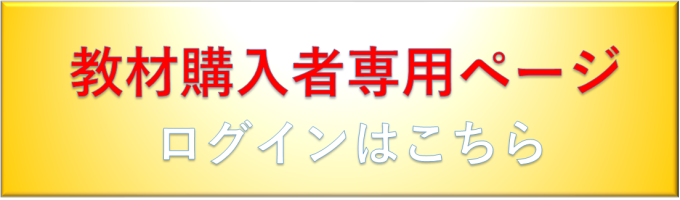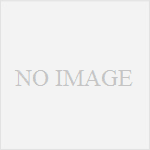一昔前であれば、民法を捨てる、また、民法の勉強範囲を絞っても、宅建業法などでカバーすることによって、宅建士試験に合格することができました。
しかし、今の宅建士試験では、受験生のレベルが高くなっており、また、法令制限なども満点を取ることが難しくなってきています。
つまり、他の科目で差をつけることが難しくなっていますので、2024年(令和6年)宅建士試験に合格するためには、民法を攻略しなければなりません。
しかし、民法は具体例形式での出題が多く、苦手な方が非常に多いです。
だからこそ、チャンスです。
理解して覚えることが重要な民法
|
【宅建士試験の問題の前提:民法】 [ケース①] 個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合 [ケース②] 個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合 |
|
【宅建士試験の問題の内容:民法】 錯誤の問題で、錯誤による取消しができるものは?という問題です。
|
|
【宅建士試験の問題の内容:民法】 取得時効の問題です。
|
この問題は、宅建士試験で出題された民法の問題ですが、見て頂いたとおり、
民法は、条文や判例を丸暗記するだけでは、本試験問題に対応することができません。
もちろん、相隣関係など単に覚えるだけで解ける問題もありますが…。
民法は、理解が必要となります。
理解が必要になる科目にもかかわらず、民法に力を入れている教材は、数少ないです。
また、そもそも、絞り過ぎていて、重要な論点を網羅していないところも多いです。
これでは、どこで勉強するのかによって、差が開きます。
是非、民法に力を入れている宅建士合格広場で合格を勝ち取ってください。
具体例なし又は絞り過ぎ教材はNG
改正民法も出題されることになって、より一層、どこで勉強するのかによって、差が開いています。
受験生の多くの方が解けない論点まで勉強する必要はありませんが、解ける論点でも取りこぼしている方が非常に多いです。
これは、受験生の方が勉強していない!というよりも、そもそも、「自分の教材には掲載されていない!」という方が圧倒的に多いようです。
これでは、差が開くことになり、また、宅建業法なども受験生の多くの方が高得点を取ってきますので、ある程度の点数を取れても、合格にはたどり着けません。
そこで、
「具体例なしの要点系の教材で勉強しない」、また、「絞り過ぎた教材で勉強しない」、また、「過去問だけの勉強はしない(過去問の解説だけでは理解できませんので・・・)」
これが重要です。
皆さんがお持ちの教材には、2025年(令和7年)10月に実施されました宅建士試験の問題50問のうち、合格点をとることができる論点が掲載されているのかどうか?を確認してください。
掲載されていない!ということであれば、その教材で勉強しないでください。
ちなみに、宅建士合格広場の教材には、掲載されています。
是非、2026年(令和8年)宅建士試験合格に向けて受かる教材で勉強してください。
|
販売教材の詳細はこちら |
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |

-e1760533051531.png)
-680x156.png)
-680x155.png)
.png)
.png)